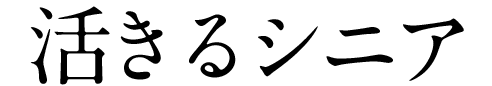在宅ケアの本質は「自宅で死ぬこと」ではなく、「死ぬまで自宅で生きる」ことである。言葉遊びのように聞こえるかもしれないが、ぜんぜん意味が違う。「自宅で死ぬ」ことは目的ではなく、「死ぬまで自宅で生きた」結果である。
先にも記したが家族にとっていちばんの心配ごとは「いざというときどうするか」である。病院や施設に入院していれば、いざというときにすぐになんらかの処置をしてもらえる」と思っているかもしれない。しかし、入院していても24時間だれかがベッドサイドにいてくれるわけではない。夕方には意識があったのに、夜中の巡回時にはすでに亡くなっていたということもある。老衰で亡くなるときなどはだんだん寝ている時間が長くなる。そうなると「いざというとき」がだんだん近づいてくることは医師や看護師でなくでもわかる。
昭和50年代、私の祖母が京都の自宅で老衰で亡くなるちょっと前に、往診に来ていたお医者さんが母親に「いつお迎えが来るかはもう時間の問題ですから、ご親戚の方に早いうちに来ていただくのがいいです」と言った。当時、私は高校生だったが「あぁおばあちゃん、もうすぐ死んじゃうんだ」と思ったのを覚えている。それから連日、叔父や叔母たちが東京や神奈川からやってきた。父親は毎日、祖母を気にしながらも会社に行っていたし、私もその日がいつ来るのか気にしながら落ち着かない日を過ごした。学校から帰ってきては「おばあちゃん、まだ大丈夫?」と部屋をのぞきに行った。母親も静かに日常生活を送っていた。
そしてその日はやってきた。夜の9時ごろだったか、テレビを見ていると父親が「おばあちゃん、亡くなったみたいだ」と祖母の部屋から出てきた。母親は夕方に様子を見に行ったときにはまだ寝息があったのに、と言いながら、私たちと祖母の部屋に行った。それからお医者さんに来てもらい診断をしてもらった(今思えば「死亡診断書」を書いてもらったということだろう)。こうして思い出すと今から40年ほど前だが、死は日常生活のすぐ隣合わせにあったような気がする。「家で死ぬ」ことが当たり前だった時代だったのだ。
亡くなるに至るまでも今でいう認知症もあった。突然家から姿を消した祖母を探しに近所を探しに行ったことも何度かあったし、保護されて警察から連絡をもらったこともあった。当時は老人施設は今ほどなかったし、家で看取るのが当たり前の世の中でそんなものだと思っていた。そういう日常を過ごすなかで家族が「祖母の死」に向かうプロセスを受け入れながら「その日」に向かって覚悟を固めていけたのかもしれない。
この数十年で世の中は家で死人を出すことに免疫がなくなっている。家族に「いざというとき」の覚悟が固まっていないと自宅で死を迎えたときにうろたえてしまうだろう。本人の呼吸が止まっていたり、弱くなっていることに気づいてパニックになって救急車を呼んでしまうかもしれない。訪問診療や訪問看護を受けていれば、もし死が近づいている兆候があればプロの目が見逃さずに、その他ときの対応を事前に話し合っておくことができるが、それができていないとあわてて救急車を呼んでしまうかもしれない。
そうなると救急隊員は本人や家族が望んでいなかったとしても蘇生に向けて手を尽くす。それはそうだろう。呼ばれて来ているのだから。消防庁の基準は生命に危険があれば応急処置を行うことを規定している。また救急車が到着したときにすでに亡くなっていると救急車は遺体はそのままにして警察に連絡をして帰るしかない。ご存知のように救急車は遺体を搬送することはできない。警察が来ると事件性を解明するために現場検証と家族への聞き取りが行われる。そうなると本人と家族との最後のお別れはあわただしいものになってしまう。そんなことがないように在宅ケアを行う場合は、信頼できる訪問看護師と訪問診療をしてくれる医師を見つけておきたい。彼らは「自宅で最後まで生きること」をサポートしてくれるプロである。
病院での勤務を経験した後に訪問看護に携わるようになった看護師が言っていた。「訪問看護で看取りをするようになって感じたことは、亡くなられた患者さんの顔や体がきれいだということです。無理な延命処置をせずに自然に亡くなると体に余計な負担をかけないせいでしょう」と。
繰り返しになるが自宅で死ぬといくことは、最後まで自宅で生きるということである。もちろん自宅での治療ができない場合はいったん病院に行けばよいのだ。大切なのは最後まで「自宅にいたい」という思いを本人と家族、そして医療従事者で支えながらそれをかなえていくことだろう。
―自宅で死ぬということ― 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は9月27日にお届けしますのでお楽しみに。