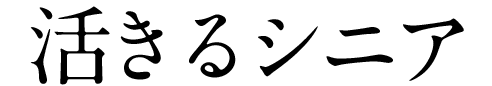Eさん 年齢:90歳 女性
病歴:誤嚥性肺炎の繰り返し
家族:娘夫婦、孫と同居
Eさんは数年前から嚥下機能が落ちて誤嚥性肺炎のために入退院を繰り返していた。最後の入院となったときには食欲もなくなり医師からは胃ろうを勧められた。入院中は鼻からの経管栄養であった。Eさんは認知機能の衰えはあったが意識ははっきりしており「もう年なのだから胃ろうや点滴で生きながらえるのは嫌だ」との意思ははっきりしていた。その後、入院を続けるなかでEさんは入院生活に不安を訴えたり、せん妄のために病院と自宅を間違ったりするようになった。付き添っていた娘もその様子を見て「家に連れて帰る」との気持ちを固めた。在宅医と訪問看護を使って在宅ケアをすることを決めた。退院時は鼻からのチューブは外さないままであった。
娘は「母親と過ごす最後の時間を後悔したくない。できるだけのことをしたい」と訪問看護師に訴えた。訪問看護師はEさんの状態を見ながら、もしかしたらまだ口から食事ができる可能性があるのではないかと感じた。そこで歯科医、在宅医と相談してVE(嚥下内視鏡検査:嚥下力があるかどうか調べる検査。自宅でできる)を行った。結果は「悪くない。経口による食事も可能」であった。娘は喜び訪問看護師と相談のうえ、経口による食事を始めることにした。娘はもともと料理が得意でありEさんも娘の手料理を食べることが好きであった。娘は母親の好みにあった茶碗蒸しや煮物、白身の魚を使った料理など心を込めてつくった。娘の思いも伝わったのかEさんは驚くほど食欲を回復させて食事ができるようになった。鼻からのチューブも外すことになった。
しかし、1か月ほどするとだんだん食欲も落ちてきた。再び鼻からチューブを入れることは本人も娘も望まなかった。食べることも飲むこともできなくなった母親を見て娘は「お母さんがかわいそう」と心を痛め、点滴でなんとかならないかと在宅医に要望した。しかしEさんの血管はすでに点滴の針も入らなくなっていた。訪問看護師は在宅医と相談して皮下注射による点滴を行った。その5日後、Eさんは静かに息を引き取った。退院から約3か月が経っていた。
もし、Eさんが退院をせずにそのまま入院を続けていたらどうなっていたであろう。消化機能がある限り鼻からの経管栄養注入は続けられ、消化機能が消失すれば点滴による栄養注入に移ったのではないかと推察される。そうすれば3か月より長く生命は維持できたかもしれない。しかし、退院したときのようにEさんが再び食欲を見せることもなかっただろうし、娘のつくった料理を味わうこともできなかっただろう。その期間はわずか1か月ほどではあったが娘は母親のために一生懸命料理をつくり、母親の食欲回復を喜び、喜ぶ顔を糧にまた料理づくりに情熱を注いだ。「後悔をしたくない」という娘の気持ちはその1か月があったことで満たされたことであろう。
目の前で親が弱っていくのを見るのはつらい。食欲がなくなりはじめたとき「点滴しなくても大丈夫ですか」と娘からの問いがなされたので在宅医は皮下注射による点滴を行った。「食べられなくなったら点滴」というのはかつての常識だった。そのため患者や家族にもその固定観念があるのだろう。しかし今は「いつまで点滴を続けるか」は医師によってもその価値観は変わりつつある。娘も点滴をされた母親を見て「これをしても母親が楽になるわけでもないんですよね」とポツリとこぼしたという。皮下注射による点滴を始めてからの5日間が娘にとってはEさんとの最後のお別れの時間になった。在宅医療は「家で最期を迎えたい本人」はもとより、「後悔なく送り出したい家族」にとっても大切な時間をもたらすということを教えてくれる事例である。
-自宅で死ぬということ- 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は1月24日にお届けしますのでお楽しみに