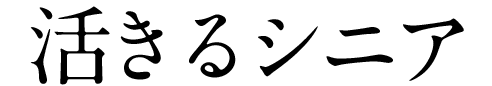「死ぬことは生きることの総仕上げ」と言われる。どのように生きるかはだれもが考える。しかし、どのように死ぬかについては声高に語られることはあまりない。2世代、3世代で暮らしていたころは「家族に見守られながら静かに」が当たり前だったかもしれない。しかし核家族が8割以上を占める現代では日常生活の延長線上で家族に見守られて亡くなることはむずかしくなっている。何かのきっかけで入院し、施設に転院し自宅に戻ることなく人生を終えること人がいかに多いことか。
自宅で死にたいと思うなら早い時期から周囲に伝えていくことが必要だ。先にも述べたが、もし死が現実的になってからだと選べる選択肢は少なくなってしまう。できるだけ元気なうちにしておいたほうがよい。入院してからだとどうしても「お医者さんに言われたとおりに」なりがちである。なにしろ入院しているということは、それだけでアウェイで戦っているようなものである。どうしても医師や看護師に「あの人は困った患者さんだ」と言われないように、言いたいことも我慢してしまいがちである。
しかし、医療界では「患者中心の医療の実践」という言葉が使われて久しいのだ。患者中心ということは、主人公は医師でも看護師でもない。患者が主人公ということだ。だが現実は患者が主人公の自覚がないまま、共演者である家族や医療従事者が主人公の運命を握ってしまうことも多い(しかも遠慮がちに)。
では主人公はどうふるまうべきなのか。主人公は自分の人生のあらすじを決めなければならない。そして周囲の人たち(共演者)とともに人生の最終舞台を迎える準備を進めることだ。そのために共演者にできるだけうまく助けてもらうことだ。家族も医師も看護師もケアマネジャーもみんな共演者である。「患者」という役割を果たすのではなく「主人公」として最後まで生きるのだ。だれかにお任せするのではなく、自分の人生のエンディングをどうしたいのかをできる限りを自分でイメージしておく。主人公がどうしたいかを伝えることができれば、共演者はフォローやサポートがしやすくなる。その伝える力こそ「患者力」である。主人公に患者力があるほど共演者はやりやすい。元気なうちにぜひ患者力を磨いておくことだ。
具体的には先に記したようなこと(6.本人が元気なうちに話し合っておきたいこと)を考えて周囲と共有しておくことだ。日常会話の時間がある人は話しておく。そのような機会がない場合は書面にまとめておいて顔を合わせたときに伝えるのがよい。すべてを詳細に決めておくこともない。自分でやりたいこととどうしてもやりたくないことを明らかにしておくだけでもよい。気持ちが変われば書き換えればよい。年配の方は「周りに迷惑をかけてしまうかもしれないから、そんなにわがままも言えない」という方も多いと思う。しかし、言ってみてできないことであればそのとき次善策を考えればよいのではないか。またそういった思いを伝えておくことによって家族にとっても「悔いのない介護」ができることにもつながる。共演者である医療従事者たちはその道のプロである。医療や看護技術の進歩もあるし、医療制度の変化もある。昔はできなかったことも、今はできるかもしれない。
人はいずれ死ぬのである。「病院でできるだけの延命治療をしてでも1日でも長生きしたい」というのであれば、それもできる。逆に「延命治療はせずに、最後はできるだけ苦しみがないように自宅で亡くなりたい」というのであれば、その意向に合わせた治療と看護をしていくことができる。病院でやれることと自宅でやれることには違いがある。そもそも病院は「病気を治す」ところであるから、病院にいる限りは最後まで病気と闘う選択をすることが前提となる。しかし「病気とは戦わない」という選択をするのであれば、退院して自宅で過ごし、やれることをしながら人生の最終舞台を迎えることもできる。自宅で死ぬということは「本人が望まない治療は受けない」ことを選択するにもなる。たとえば自宅で訪問看護を利用する場合、「苦しい食事制限はできるだけ避けたい」「生きているあいだに好きなものを食べたい」という願いがあれば、訪問看護師が相談にのり家族とも相談しながらそれをかなえることもできる。
家族にとっては「もし自宅で看護をしたら、いざというときに家族だけでは対応できない」という不安もあるだろう。これもパラダイムの変換が必要である。「いざというとき」に何を求めるか。救急車を呼んで病院へ運んで人工呼吸器を装着すれば延命治療のスタートになるかもしれない。それは果たして本人が望んでいたことなのかどうか。ここが自宅で看護する際、いちばん大きな問題になる。「自宅で看取る」という家族の覚悟があれば、「いざというとき」に向けて訪問看護師、医師とで準備や話し合いを進めておくこともできる。
病院にいても、自宅にいても人は死ぬときは一人である。自分の人生の最期をどこで迎えるか。主人公(本人)が決め、その意向をかなえるのも共演者(家族)の最後の役割ではないだろうか。
―自宅で死ぬということ― 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は9月13日にお届けしますのでお楽しみに。