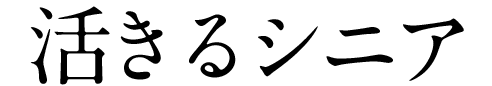近くの「かかりつけ医」をつくっておこう
訪問看護はいろんな使い方ができることを紹介してきたが、そろそろまとめに入ろう。訪問看護を活用するには利用者がその知識をたくさんもっていることに越したことはないが、実際はどこまで知っていれば良いのかさえわからないだろう。したがって「知識をもった人」と「頼れる人」とつながっておくことである。そのためにまずは信頼できる訪問看護ステーションを見つけておくことは繰り返し書いた。そしてもう一つは近くの「かかりつけ医」をつくっておくことである。なぜなら訪問看護は基本的に医師の診断のもとに看護計画(ケアプラン)が組み立てられるからだ。前回述べた「訪問看護指示書」は該当の利用者に対して「主治医」が発行するものだったことを思い出してほしい。いろんな制限から外れて訪問看護を受けることができる「特別訪問看護指示書」も同一の医師から発行されるものである。
今後、大きな病院に直接行ってすぐに診断を受けることはなくなる。大規模病院、中規模病院、地域のクリニック(医院)では機能がますます分化される。さらに今回のコロナ禍でもわかるように大規模病院に行くことは高齢者にとって感染のリスクもある。「最初の診断は近くのかかりつけ医に」が鉄則だ。かかりつけ医には次の5つの役割がある。①適切な他の医療機関の紹介 ②健康診断・健康相談 ③介護保険の主治医意見書 ④地域での活動、在宅医・ACP ⑤認知症の早期発見と支援(東京都医師会HPより)。かかりつけ医は地域連携しているから、そこから評判の良い訪問看護ステーションを紹介してもらうことももちろんできる。
最後におさらい
自宅で死ぬためにはかかりつけ医と訪問看護ステーションをうまく使うこと。その最初の一歩を踏み出しやすいように基本的なおさらいをしてまとめとしたい。
■料金はどれくらいかかるのか。
訪問回数や滞在時間で基本料金が決まる。医療保険、介護保険ともに自己負担額が決められている。利用の状態によって加算(追加料金)がある。また疾患によっては公費負担もある。事前に確認しておくとよい。
■訪問看護は一人暮らしでも利用できるのか。
できる。訪問看護師だけではなく、医師、ケアマネジャー、介護士、理学療法士などいろんな職種が協働してサポートする。遠く離れて一人暮らしをする親も訪問看護ステーションを使ってサポートできる。
■リハビリテーションも訪問看護でできるか。
できる。訪問看護ステーションによっては理学療法士、作業療法士による訪問リハビリテーションを行っている。また看護師によるリンパマッサージ、オイルマッサージ、アロマテラピーなどを行っているところもある。これらによって浮腫(むくみ)や疼痛管理(痛みの軽減)、寝たきり防止、自律神経の安定などの効果も期待できる。そういった取り組みをしているかもステーション選びの一つの視点にもなる。
■看護だけでなく身の回りの世話もしてもらえるのか。
医療保険を使ってできるのは「看護行為」に限られるが、介護認定を受けていれば介護保険を使って「訪問介護サービス」として「家事援助」が受けられる。ただし保険内でできることには制限がある。保険範囲外のサービスを利用者の全額利用者負担で行っているところもある。
■医師による往診や病院への付き添いもしてもらえるか。
往診はまず「かかりつけ医」に相談するべきだが、多くのステーションが往診のできる医師と提携をしている。病院への付き添いは医療、介護保険ともに保険の範囲内ではできない。保険外扱いのサービスとして全として額利用者負担で行っているところもある。
■緊急時、深夜、早朝の訪問や訪問時間の延長はできるのか。
「24時間、365日対応」を謳っているステーションであればできる。「夜間・早朝訪問加算」「深夜訪問加算」「緊急訪問加算」「長時間訪問看護加算」などで追加料金が必要だ。事前に料金一覧などを確認しておくのがよい。
■赤ちゃんや子どもでも訪問看護は受けられるのか。
0歳から受けられる。ただし、ステーションによって対応できる体制があるかどうか事前確認は必要。
■どんなに遠いところでも来てもらえるのか。
ステーションごとにサービス提供エリアが決まっている。そのエリアを越えてのサービスを行っているところもあるが、ほとんどの場合、交通費は実費請求される。
■身体障碍者手帳、自立支援受給者証をもっているが利用料はかかるか。
身体障碍者は加入している健康保険の割合額がかかる(介護保険は1割自己負担)。
自立支援受給者は利用するステーションを「指定医療機関」として申請すると原則1割自己負担になる。
■生活保護を受けていても利用できるか。
自己負担なくできる。
■ドレーンチューブや留置カテーテルを使用しているが利用可能か。
できる。「特別管理加算」という追加料金がかかる。事前にステーション側と打ち合わせする。
■精神疾患があるが利用可能か。
できる。「精神科特別訪問看護指示書」を医師に書いてもらう。事前にステーション側と打ち合わせする。
1年間にわたり連載という形で「自宅で死ぬという選択をするには、どのような意識と知識がもっておくのがよいか」をお伝えしてきた。2020年4月現在、新型コロナウイルス感染予防対策のため病院にいくことさえままならぬ状態になっている。病院にいること自体がリスクであることがより真実として浮かび上がってきている。
このコロナ禍が過ぎた後、日本の医療環境がどうなっていくのか、今の時点ではわからないが、間違いなく「病院は病気を治すところ」であることがさらに進み、一人ひとりが自分の健康や命をセルフケアし、持てる自己の免疫力を高め引き出していくという方向になることは間違いないだろう。
そして自宅で死ぬという選択が当たり前になっていくのではないだろうか。その選択をする際にこの連載が少しでもみなさまのお役に立てることを願う。
ご愛読ありがとうございました。 小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※本連載に対するご感想や質問があればぜひメールでお送りください。回答できるものに関しては、このWEBサイト上または直接メールでさせていただきます。
メールアドレス info2@nscd.or.jp