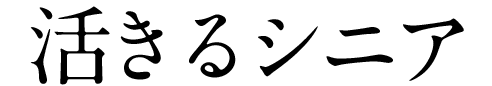Oさん 年齢:60歳 男性
病歴:肺がん
家族:妻、長男(30代)と3人暮らし
Oさんは50代で肺がんを発症した。治療を受けながら仕事を続けたが入退院を繰り返した。それでもなんとか定年まで仕事を続けることができた。それがOさんの目標でもあったのだろう。定年を迎えた後は緊張の糸が切れたかのようにOさんは体調が悪くなった。
病院ではこれまでできる限りの治療を受けてきた。末期がん患者として再び入院したOさんは病院のベッドで酸素吸入をしながら過ごす日々となった。医師は妻に「もう病院でできることはありません。最後はご自宅でお過ごしになってはいかがでしょうか」と告げた。それは妻にとっては最終宣告のように聞こえた。病院においては「病気で死ぬことは敗北」のように医師が感じているように思えた。ナーバスになっていた妻には「もう夫にはこれ以上の治療はないのだ」と思うと突き放されたような気がした。しかし、寄り添ってくれた看護師が「患者として病院におられるより、家族の一員としておうちに帰られたほうがご本人も喜ばれるかもしれませんよ」と言ってくれたことに気持ちが落ち着いた。病院にいたら患者としてもう死を待つだけだが、家に帰ればまだ家族としてやれることがあるのではないかと考えが変わり始めたと言う。
医療の場所にいる限り「患者」であり、家族は治療に関してはどうすることもできない。「水が飲みたい」と言っても飲ませていいかどうかを看護師に聞かないといけないような気持になる。しかし、もし家に帰ればまずは「家族」であり、夫が望むことは夫と自分の判断でできる。夫はこれまで病院で医師の指示に従いがんばってきたのだ。もう病院でできることがないのであれば、闘病はやめて自宅でゆっくり過ごさせてあげようと妻は決意した。30代の息子は仕事が忙しく病院への見舞いはなかなか行けなかったので父親が自宅に戻ってくることを喜び歓迎した。
Oさんも自宅に帰れることを喜んだ。家に帰るとそれまで病院では口にしなかった家族への感謝の言葉や、自分が亡くなった後の保険のことを話し始めた。もちろん妻や息子に不安がなかったわけではない。そこで訪問看護師は1日2回の訪問をして「Oさんの看護は私たちに任せてください。奥さまはそばにいてOさんにしてあげたいことをしてください」と伝えた。夜間にOさんの呼吸に異変を感じたときは遠慮なく電話をするように言いサポートをした。自宅に戻って数週間後、Oさんの意識は亡くなり眠るように穏やかに旅立った。最後はOさんがいちばん好きだったゴルフウェアを着て荼毘(だび)に伏した。
妻は言う。「入院していたときは、いつ亡くなってしまうかと不安でした。でも自宅に帰ってからいつでも声を掛けられたし、様子を見ることができたからだんだん覚悟ができてきました。死を受け入れる心の準備ができていたのかもしれません」と。
病院は病気を治すところであると再認識すると、闘病にがんばる入院生活はどこかで終止符が打てることもある。そこからは自宅に戻って家族としてやれることが残っているのであればそれを選択してもよいのではないだろうか。
-自宅で死ぬということ- 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は2月28日にお届けしますのでお楽しみに。