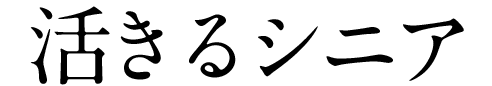Hさん 年齢:83歳 男性
病歴:心不全、前立腺肥大
家族:妻は特別養護老人ホームにいるため一人暮らし。子どもはない。兄弟とは縁遠く付き合いなし。
Hさんはかつてマスコミで仕事をしており、自分の意見や主張をはっきり言う人だったらしい。加齢とともに耳が聞こえにくくなり周囲とのコミュニケーションがとりにくくなっていた。肺炎で入院した際に看護師との何度か意思の疎通が図れないことがあったようだ。たとえば、本人は耳が聞こえにくいのは補聴器が壊れているせいだと伝えているのにそれが看護師には聞き入れられなかった。さらにコミュニケーションができないのは認知症のためだと診断された。
その後、特養に移されたが本人は「家に帰りたい」と言い続けていた。そこで訪問看護ステーションが介入し自宅で週に2回の訪問看護で服薬管理、体調管理を行い、掃除、洗濯は訪問介護を利用することで在宅ケアを行うことになった。自宅はかなり荒れており「ゴミ屋敷」状態に近かったが、本人はモノの置き場所などは把握していたのでヘルパー、訪問看護師が連携をして整理整頓を進めた。前立腺肥大のため紙オムツを使用していたが、尿漏れを起こしていることもあり、訪問看護は1回の訪問でふつうより時間を多めにとって処置を行うことにした。
訪問看護を行うなかで看護師は認知症と診断されていることに違和感を覚えた。なぜならHさんはちゃんと会話を理解しており、言っていることも辻褄(つじつま)があっているのだ。ただ難聴のためにそのコミュニケーションに時間がかかる。本人にしてみれば「なぜわかってくれないのか」との怒りの感情とともに自尊心も傷つけられていたようだ。病院では認知症と診断されていたが、訪問看護師の見立てでは年齢的な認知機能の低下は認められるものの認知症と診断されるほどではない。相手の言うことが聞こえれば会話は成り立った。Hさんは「病院ではだれも自分の言っていることを聞いてくれようとしない。あそこは“収容所”だ。私を送り込んだケアマネジャーを一生うらんでやる」とかなりの剣幕であった。このような訴えもいったん「認知症だ」というレッテルを貼られてしまうとなかなか正面から受け止められにくくなるのが現実だろう。逆に「困った患者さん」としてひとくくりにグループ分けされて、そういった対応をされてしまう。
「それをきちんと診断するのが病院の役目ではないか」という指摘は当然あるだろう。しかし、それがしにくいのも昨今の病院の現状でもある。医療費抑制のために入院期間は短縮化されている。その期間では当然、看護より治療が優先されてしまう。「時間薬」という言葉がよく使われるが、病院では時間薬は処方されない。それぞれの患者ごとに看護計画が立てられるが、それがすべて達成されてから退院をするわけではないのだ。看護計画が達成されないまま入院期間は終わり退院していく。残された看護課題はどうなるのかと言えば、本来は家庭に戻り、本人(と家族)がそれに向けて継続してセルフケアをするということになるはずである。自宅で質の高い看護を保ち続けることができればよいが、できなければ病状が悪化して再度入院となる。そして入退院を繰り返していくうちに病院で最期を迎えるということが多い。
「ときどき病院、ほぼ在宅」という言葉を前に紹介したが、そうなるためには「ほぼ在宅」への意識転換が必要だ。病院に勤める看護師も患者の退院後の生活までに関われるような体制があればよいが、業務の分業化がされている病院ではむずかしいだろう。だからこそ病院と訪問看護ステーションが連携をして看護計画を継続できるようにしていくことが必要である。
念願の在宅ケアに戻ったHさんは、在宅酸素を必要としている状態でも酸素なしで外出して映画を見に出かけ楽しかったことや、お風呂が大好きだったので1人で銭湯に出かけてその風貌から入店を拒否されたことを憤慨しながら話すなど、訪問看護師を驚かせた。しかし喜怒哀楽のある自由な生活を送れたのではないだろうか。その後、心不全の悪化と緩解を繰り返し終末期を迎えた。そのころには看護師もヘルパーもほぼ毎日訪問し、最後は自宅で亡くなられた。
高齢化によって認知機能の低下が認められるのは仕方のないことである。しかし、それを「認知症」としてとらえてしまうと、本来見えるべきものが見えなくなってしまうことがある。医師、看護師、家族……それぞれの視点から見ることも大事である。とくに医療スタッフは本人とそれまでの接点がなければ、その人となりを知らない。Hさんは若いころからマスコミ業で自分の主張を訴えてきた人であった。自分の訴えが受け入れられないことが入院中は腹立たしかったのだろう。訪問看護師とのコミュニケーションがとれたことによりHさんも落ち着くことができた。Hさんは独り暮らしであったがもし家族が近くにいたら認知症の診断ももう少し慎重にされたかもしれない。
-自宅で死ぬということ 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は11月8日にお届けしますのでお楽しみに。