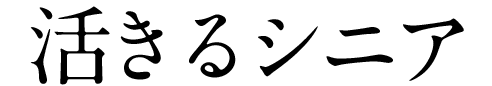Tさん 年齢:79歳 女性
病歴:がん(終末期)、心臓病、認知症
家族:70歳で離婚。娘1人、息子2人がいるが独立しており独居。娘1人とは絶縁しており30代の息子が遠方から世話をしていた。
Tさんは入院中から認知症があった。しかし身の回りのことは自分でできたため、最初は退院をして一人暮らしをしていた。だが心臓病を発症して入退院を繰り返すうちにADL(日常生活動作)が落ちてきて退院をすることがむずかしくなってきた。治療には服薬をすることが絶対条件であることもありケアマネジャーが面談したところ「認知症もあり在宅で本人が定期的に服薬することはできないと思われる」との判断がなされた。
息子は「本人の気持ちを大事にしたい」と病院に掛け合ったため、病院側から訪問看護ステーションに相談がなされた。訪問看護ステーションでは「毎日の訪問を行えば一人暮らしも可能である」としてTさんの在宅ケアが始まった。
訪問看護は毎日、ヘルパーの訪問は食事の用意などを中心に当初は週に3回であった。看護師は回想法などを用いて認知症が進まないようにした。回想法とは写真や映像を見ながら過去を思い出したり、いろいろな会話を通じて人生を振り返ることで脳を活性化させたり気持ちを落ち着かせる認知症リハビリテーションの手法である。それ以外には特別な看護をしなかったことが本人の自尊心を傷つけなかったと思われる。
退院前は、入院時の姿から「認知症のために身の回りの整理整頓はできないであろう」と見立てられていたが、実際に自宅に戻り生活する姿を訪問看護師が確認したところ、Tさんなりの秩序がありそのなかでの整理整頓がなされていることがわかった。ADLに関連する買い物や掃除、服薬やお金の管理、趣味の活動や公共交通機関の利用や電話をかけるなどの幅広い動作をIADL( Instrumental Activities of Daily Living)というが、ぎりぎりまでIADLを保つことができた。一人で入浴することもでき、在宅ケアは思いのほか順調だった。電車で2時間ほどかかるところに住んでいた息子だが、折に触れて母親に電話をし、週に1回以上は訪問を続けた。
途中何度かの入院や自宅室内での転倒もあり、ケアマネジャーやヘルパーからは「やはり在宅ケアは無理ではないか」との意見も出たが、息子は「父の思うような最期を」という願いが強く訪問看護師、ケアマネ、ヘルパーでその都度、話し合いを行った。その結果、ヘルパーと看護師の連携は試行錯誤が続いたが約2年間在宅ケアを続けることができた。
終末期の1か月は心不全とがんの悪化により体力も落ちたので毎日、朝晩の訪問看護と昼のヘルパー訪問を行いつねに目が届くようにした。最後は自宅で息を引き取ったが、本人は一人暮らしをすることにより入院時よりも気力、体力とも回復できていたと思われる。自分ががんであることも自覚していたが「100歳まで生きていたい」と訪問看護師に話しかけることもあった。
この事例でわかることは、入院中の姿からだけでは必ずしも「在宅ケアはできない」とは言い切れないということである。もちろん施設では看護師やケアマネジャーがその姿から退院後を想像しながら判断をするのでそれを疑えということではない。ただ、彼らは施設内看護の専門家ではあるが在宅ケアの専門家ではない。家に帰ることで患者が施設内では発揮できなかった力が引き出されることがある。また「自宅に戻った限りは自分でなんとかしなければならい」という気持ちが患者に芽生えることもある。病院のようにナースコールを押せばすぐに訪問看護師がやってくるということもない。自分でなんとかやってみようという気持ちの張りが施設にいるときとは違う力を発揮させるのかもしれない。
本人に自宅に戻る気持ちが強く、ある程度、身の回りのことができるのであれば退院前に訪問看護ステーションに相談して在宅ケアの可能性を探ってみることも一つの手である。
-自宅で死ぬということ 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は11月22日にお届けしますのでお楽しみに。