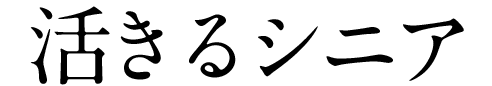Jさん 年齢:90歳 女性
病歴:認知症、末期内臓がん
家族:夫とは十数年前に死別。娘がいるが絶縁状態。連絡がつくのは親戚の男性Kさん(30代)のみ。
Jさんは夫と死別してからは一人暮らし。娘とは連絡をとっていない状況のなかで認知症を発症。かろうじて親戚の男性Kさんと連絡がとれるのみだった。ヘルパーが食事や洗濯のお世話をしていたが、亡くなる数か月前から体調不良を訴えたためヘルパーがKさんに連絡を取り最寄りの市立病院に連れて行った。外来で末期の内臓がんと診断され、体力も衰弱していることからその場で入院を勧められた。しかしJさんは大声を上げてかたくなに拒否して帰宅。困った病院から訪問看護ステーションに在宅ケアが可能か相談があった。
訪問看護ステーションの管理者とケアマネジャーがJさんの自宅を訪ねると「帰ってくれ!」と最初は面会もできなかった。当時はヘルパー以外、訪問診療の医師さえも会えない状態だった。会えば「自分はどこかに連れて行かれる」という猜疑心をもっていたようだ。Kさんに相談して「市の職員」と名乗って訪問看護師がJさんと面談。ちょうど玄関の電球が切れていたので「明日に取り換えに来ますね」と約束して翌日に訪問するなどしてようやく人間関係を築けるようになった。
Jさんの自宅は昭和に建てられた2階建て戸建て住宅で、1階は仏間、リビング、キッチンであり2階は使われていなかった。各部屋には家族の若かりしころの写真がたくさん飾ってあった。小さな庭がありそこに生えた草花がいつも仏壇に供えられていた。看護師との関係構築ができていくとJさんはかつて20代の息子を亡くしたことを語った。その息子、夫、両親を「仏さん」と呼んで仏壇で供養していた。その仏壇を守ることがJさんが入院をしないいちばんの理由だったようだ。Jさんは昔の写真を見ながら家族のことをよく語るようになり、今は連絡の取れなくなった娘にも会いたいと本心を打ち明けるようにもなった。Jさんにとっては一人暮らしであっても自宅はかつて家庭のあった場所であり、気持ちとしては一人ではなかったのであろう。体力が落ちていくなかで看護師は何度か「入院をしたほうが楽になるのではないか」と入院の意思を確認したがJさんは首を縦に振ることはなかった。それでも一人で家にいることはさみしいらしく、看護師が訪問した際には「よく来てくれた」と喜び、帰る際には「帰らんといて」と手を握ることもあったという。
訪問看護を始めたころは体力的にはまだ一人で出歩くことも可能ではあった。しかし認知症があることから外出先で帰宅不能にならないように訪問看護師は「地域見守り隊」をつくった。具体的にはJさん宅の向こう三軒両隣を訪問しJさんの状況を伝えて、もし近所で姿を見かけたときは声を掛けたり自宅まで送ってあげてほしいと頼んだ。昔から近所付き合いがあったことからみな快く受け入れてくれた(そのおかげで外出中に体力がもたず帰れなくなったJさんを近所の方が見つけて自宅まで送ってくれたこともあった)。
要介護2でヘルパーは毎日訪問して「身体介護(清拭や排せつ)」「生活介護(食事や掃除)」を行ない、訪問看護は週に3回、体の状態のチェック、がんの痛み止めの薬や水分がきちんと飲めているかなどの管理と本人の話をよく聞くことに徹した。時間の経過とともにJさんの体力は落ちていき、家の中を歩いて移動することも困難になってきた。看護師が訪問するとJさんは布団で寝ているだけでなく、仏間、キッチン、玄関などいろんなところで倒れるように寝ていることも多くなってきた。そこで看護師はどこで転倒してもケガをしないように布団を家中に敷き詰めた。訪問看護師は「どうやら一人のときは這うように家の中を移動して“自宅での生活”をされていたように思います。布団で寝ているだけでなく、ときにはリビングに行って家族の写真を見ながら語り掛けたり、玄関の様子を見に行ったり。病院のベッドの上にずっといるよりご本人は幸せだったのではないかと思います」と。
自宅で死ぬということは、その人にとってはそれまでの人生を歩んだ家族やご近所さんとの関係性の中で最期を迎えるという意味がある。たとえ一人暮らしでもJさんは亡くなった息子さんや夫や両親の供養をしている仏壇を守ることが人生の最後のおつとめだと思っていたのだろう。「畳の上で死にたい」と生前から言っていたJさんは、自宅に介護ベッドを入れることもなく文字どおり自宅の畳の上に敷いた布団で亡くなられたという。本人の望みどおりの最期だったのではないか。
-自宅で死ぬということ 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は12月13日にお届けしますのでお楽しみに。