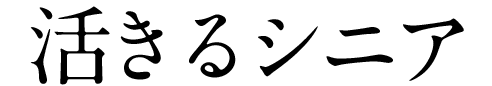Mさん 年齢:70歳 女性
病歴:認知症、胃がん
家族:夫とは死別。徒歩圏内に結婚して家を出た娘(50代)が住む。
Mさんは夫と死別してからはずっと一人暮らし。軽度の認知症を発症していたが生活全般には問題なく、ヘルパーの助けもなく生活をしていた。近所に結婚して家庭をもった娘がおり交流があった。あるとき体調を崩し病院に行くと胃がんが見つかった。医師は手術は勧めず薬で治療していくことが良いのではないかと娘に伝えた。仕事をもつ娘は「自分が自宅で母親の面倒を見るなど絶対に無理。どこかのタイミングでホスピスに入ってもらうようにしたい」と訪問看護師に訴えた。
この時期から週1回の訪問看護が始まったが、Mさんは認知症のせいか自分ががんと診断されたことも忘れたようでその後も一人で生活全般をこなすことができた。痛みもさほどなかったようで病院に行きたいなどの訴えもなかった。がんの影響で腹水がたまるのだが、自身ががんである認識がないため「なんでこんなにお腹が張るのかしら」という訴えを娘や訪問看護師にするのであった。
娘はそろそろ「ホスピスに入院を」と考えたが、本人の様子を見ていると言い出すタイミングを見つけられずにいた。訪問看護師は「ホスピスに入るにしてもご本人が納得されることが大事。今はまだそのタイミングではないのではないか」と伝えた。「本人は認知症なのだから病院でも自宅でも入ってしまえばわからないのではないか」というのは家族によくある初歩的な誤解の一つである。認知症であっても本人の意志は必ずある。納得しないまま施設に入っても自分の意志に反したことはわかる。看護師は服薬による痛みのコントロール、体の状態(血圧や脈拍など)を観察して訪問看護を続けた。
仕事をもつ娘にとっては自宅で母親を看取るなどそれまで想像もできなかった。しかし、入院するつもりなどまったくない母親と面と向かうとホスピスに入ったら?などと言い出すことはできなかったし、実際の母親の暮らしを見ていると一人でもそれなりに生活はできており、無理して入院することもないかと思うことも増えてきた。娘がもっていた「人は家で死ぬものではない」という意識が薄れてきたせいでもある。
しばらくするとMさんの体力はガタンと落ちた。その状態に合わせて訪問看護師は毎日訪れるようになった。Mさんからも「息をするのがしんどい」との訴えが出てくるようになった。心不全のせいか呼吸がゼイゼイと聞こえるようになり食欲もなくなってきた。訪問看護師はその様子から死が近づいていることを予感した。しかし「この状態でホスピスに移れば、かえってMさんの体に負担がかかり死期を早めることになりかねないし、娘さんとの最後の時間をゆっくり過ごすこともできないであろう」と感じた。そこでありのままにその思いを娘に伝え、さらに「それでもホスピスに入院させたいと思ったらいつでも言ってくださいね。すぐに手配をしますから」と最後までサポートすることを約束した。
Mさんはだんだん衰弱していったが最後までコミュニケーションはとることができた。娘はMさんが亡くなる一週間前から仕事を休み、いっしょに過ごし最期を看取ることができた。娘は訪問看護師に「家で看取ることができて本当に良かった」と繰り返して伝えた。
はじめは母親をいつホスピスに入らせるかばかりを考えていた娘であったが、Mさん本人が最期まで家で過ごす強い気持ちをもっていたことと、実際にMさんが1人で生活する努力を続けていたことを見て、娘もそれを最後までサポートしようという気持ちに変化したようである。また訪問看護師が「いつでもホスピスに入れる手配をしますよ」と伝えたことで安心感が生まれ、それがかえって母親を家で看取る覚悟につながったのではないだろうか。本人と家族の気持ちが一致して、そこに医療スタッフと地域施設との連携ができれば在宅ケアへのハードルはもっと低くなると感じられる事例である。
-自宅で死ぬということ- 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は12月27日にお届けしますのでお楽しみに