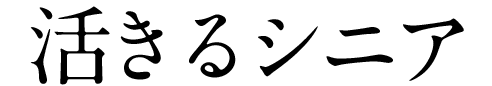私は昭和37年に生まれた。自宅で祖母が老衰で亡くなったとき、私は高校2年生だった。当然のように家に葬儀屋さんが来て、玄関に敷物が敷かれご近所さんが訪問者の受付をしてくれた。家の近くでもそのようなお葬式はたびたびあったし、霊柩車が街中を走るのを見かけると当たり前のように親指を隠して握った。しかし、いつからか近くに儀典会館ができて、家でお葬式をやるという風景を見ることがなくなった。マンションが増えたこともその理由の一つであろう。同時に「家で死ぬ」ということ自体がめずらしくなってきている。核家族、共働きが当たり前になり、高齢者を家で看取るということも減ってきた。慢性期疾患患者、認知症患者が増え家で療養をすることができなくなると、高齢者は老人保健施設や特別養護老人ホームで晩年を過ごすことが増えてきた。そして特養に入れば、人生の最後をそこで迎えるというケースが当たり前のようになってきている。
しかし、超高齢時代が間もなく到来する現在、病院や施設のベッド数、入居枠が不足してくることが予測されている。厚生労働省では2003年(平成15年)から病院は「早期回復の促進をする場所」として、入院期間の短縮化を図ってきているし、2018年の診療報酬の改定では2025年問題を見据えて「地域包括ケア(病院と地域が連携して患者を病院から地域に戻すシステム)」の準備を進めている。そうしなければもう病院や施設はパンクしてしまうからだ。
昭和前半は「家で生まれて家で死ぬ時代」
昭和後半は「病院で生まれて家で死ぬ時代」
平成は「病院で生まれて病院で死ぬ時代」であった。
令和は「病院で生まれて家で死ぬ時代」になっていくはずである。
そうなったときに必要なのが「在宅ケア」、家で患者をケアすることである。
家で死ぬ時代が再び戻ってくる。しかし、社会の仕組みは昔とは変わっている。昭和の時代にはなかった介護保険制度があるし、各種施設もある。それらをうまく活用することが必要になってくる。そのためには医療や看護を医療従事者に任せきりになるのではなく、医療従事者とともにケアにかかわっていくことが求められる。
病院に家族を預けているとどうしても「先生のご判断にお任せします」というスタンスになってしまいがちである。もちろん医療従事者はその道のプロフェッショナルであるからそれぞれの立場でいちばんよい判断をされるであろう。しかし、患者として、患者の家族としてどのように死を迎えるかを医療従事者に任せっきりにしてよいのだろうか。それを再び考える時代になるのである。医療はどんどん進化している。命を伸ばす医療技術はこれからも発展していくことは間違いない。その分だけ人間も「どのように死ぬか」を考えて自分たちに必要な医療を選択していく時代になるのである。
―自宅で死ぬということ― 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は5月24日にお届けしますのでお楽しみに。