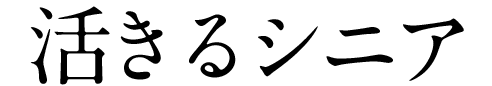とは言うものの、実際に年老いた親を自宅で看取ると考えると本当にそんなことが可能なのかと思ってしまう人がほとんどではないだろうか。
ここからは私の体験である。私の両親は京都で二人暮らしをしていた。兄は関東に、私は大阪にそれぞれ家庭と仕事を持ち忙しい日々を送っていた。父親が80歳を超えて脳梗塞を起こして救急車で運ばれて入院。そこから86歳で亡くなるまで父が家に帰ることはなかった。転院→老健→脳梗塞→入院→転院→特養→脳内出血→入院→転院→転院→転院、そして永眠。
特養でお世話になっているとき、当時高校生だった私の長男がお見舞いに行くと父親はうれしそうな顔をしながら「おじいちゃんが今度退院したときは、もう一度キャッチボールをしよう」と話していた。父親は家に帰りたかったのだ。しかし正直なところ、私はもう父親が自宅に帰ってくることはないと思っていた。もしも父親が戻ろうものならだれがいったい面倒を見るというのだ。母親もすでに80歳を超えており足腰が弱っている。自分は大阪での生活を変えることはできない。父親には悪いが我慢してもらうしかない、そんな気持ちだった。もちろんできることはやったし、休みのたびに見舞いにも行った。そして父親は最後の転院をした2週間後息を引き取った。私はまだまだ父親は生きると思っていた。転院をしながらも容体が落ち着けば、また特養に戻れるのではないか、あと数年は生きてくれるのではないかと楽観的な気持ちでいた。当たり前だが肉親を亡くすという経験をしたことがないのだから現実的にとらえることを自然に避けていたのだろう。
父親が亡くなってしばらくは「やれることは全部やった」と思い、後悔はまったくなかった。今度は一人暮らしになった母親をサポートする番だ。相続などの手続きをしながら母親と話をする機会が断然増えた。そのなかで母親は何度となく「私はできるだけ家で過ごしたい。お父さんみたいに病院や施設を転々とするとあなたにも迷惑をかけることになるし、私もご近所さんと会うこともできなくなる。できるだけ家でがんばって最後はコロリとお別れしたい」と言うのだ。それを聞いて私は父親が私の長男に「退院したらキャッチボールをしよう」と言っていたことを思い出した。父親は帰りたかったのだ。しかしそれを私には言えなかったのだ。なぜなら私がそれを聞きたくないそぶりを見せていて、父親にもそれがわかっていたから。そこから私の胸はうずき始めた。思い起こすと父親は帰りたいサインをいろんなところで出していた。そしてそれを私はことごとく見て見ぬふりをしていたのだ。
そこから私は母親にはそんな思いをさせたくないと思い始めた。昭和初期に建てられた実家は段差が多く改築・増築で生活の動線も悪かった。広い庭も父親が元気なときは家庭菜園でいろんな野菜や花を育てていたが手入れをできなくなっていた。将来的に私が戻ることも見据えて思い切って土地を半分売却して、バリアフリーの家に建て直した。そこで今、母親は一人暮らしを続けている。
「そこまでしたならなぜ同居しないのか」という人もいる。こう書くと怒られるかもしれないが、大学を卒業してから親と離れて暮らしている私にとって、もう一度親といっしょに暮らすというのはハードルが高い。お互い生活のペースも違うし、親子といえども価値観も違っている。しかし母親の人生を尊重はしたい。幸いなことに母親はいろいろ体に悪いところはあり要介護3認定ではあるが、足腰が弱っている以外は現時点ではヘルパーさんの力を借りてなんとか一人暮らしできている。母親にはこれからもできるだけ家で過ごしてもらい、家で看取りたいと思っている。準備をするタイミングがあるとするなら親がまだ一人暮らしできている今だ。
―自宅で死ぬということ― 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は6月14日にお届けしますのでお楽しみに。