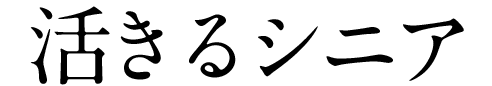2020年の高齢者(65歳以上)の一人暮らしは約670万人(国勢調査2015年)と予測されている。だれにも知られずに自宅で亡くなってしまうことが「孤独死」と呼ばれているが、私が述べている「自宅で死ぬ時代」は孤独死を指すのでは当然ない。家族に見守られ、または一人暮らしをしながらも必要十分な医療・看護を受けて最後まで生き抜いた末に自宅で亡くなることを指している。
治療を受け病院でやれることはすべて終わったとき退院をするのが病院のルールである。内科であれば体温や血圧、血液検査などの数値が安定し後は薬を飲み続けることだけという場合。外科であればある程度のリハビリが終われば退院である。家族にしてみれば入院前の状態になって戻ってくることを望むが必ずしもそうとはならない。むしろ高齢者の場合、退院後の生活が以前通りに戻ればラッキーと言える。薬を定期的に飲んだりすることはかなりの割合で必要だろうし、家族にとって難易度の高いと思われるもの、たとえばストーマ(人工肛門)をつけての退院や、定期的なインシュリンの自己注射といったこともあるだろう。昔ならばその準備期間として、退院時期を少し延ばしてもらうこともできたかもしれないが、今の医療制度ではそれはない。治療ごとに決められた期間以上に入院期間が延長すると病院側に診療報酬が支払われない。したがって退院を余儀なくされるのである。
今は入院とほぼ同時に退院後のことも患者本人や患者家族は説明を受ける(これを医療側からは「退院指導」「退院支援」と呼ぶ)。このタイミングから本人や家族は退院を現実的に考えておかないといけないのだ。退院時にはどんな状態で家に帰ることができるのか。そのためには本人はどのような覚悟をしなければいけないのか。日常生活のこと、経済面でのことなどなど。
突然の入院の場合、そんなことを考える余裕はないかもしれないし、この先どうなるかもわからないときに病院側から退院後のことを話されることに対して不信感を抱く人もいるかもしれない。しかしそれが「時代の流れ」なのである。ずっと病院にいることはできない。「病院は治療をするところ」であるという認識を患者側がこれからますます強くもたねばならない。
かと言って病院からいきなり退院して自宅で生活をすることができないことも多々あるだろう。治療が終わったと言ってもリハビリを継続する場合、自宅で生活する環境(手すりがあるか段差はないかなど)を整えなければならない。
また帰るべき家で家族がすでに他の高齢者の介護をしていたり、子育て中であったりと、すぐには受け入れられる状態ではないかもしれない。
さらに終末期を迎えていよいよ自宅で最期の生活を送る場合、訪問介護や訪問看護をいかに利用するかを検討しなければいけない。
これらを解決するためにつくられているのが「地域包括ケア」というシステムである。具体的にはまず全国の病院に「地域包括ケア病棟」が2018年4月からつくられている。この病棟は患者が自宅に戻るための支援が目的で、最長60日以内の入院が可能である。この期間中に在宅医療を受ける環境を整えたり、受け入れる家族がリフレッシュをしたり、介護保険の申請をしたり、退院後利用するサービスを検討したりすることができる。そして退院後も医療スタッフが各家庭への訪問指導を行う。もちろん病状が悪くなった場合は再度入院することができる。つまり長期入院をできるだけ減らし自宅に帰ってもらうのだ。これにより国は入院患者を減らし医療費を抑制することができる。
「ときどき入院、ほぼ在宅」という言葉を聞いたことはないだろうか。これからの高齢者の医療のスタイルとして厚労省が提案しているスローガンだ。
―自宅で死ぬということ― 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は6月28日にお届けしますのでお楽しみに。