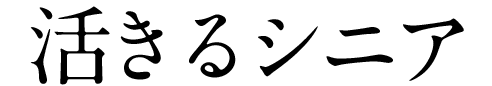病院から自宅に戻る準備について、もう少し詳しく掘り下げてみよう。とくにここでは高齢の親をもつ子どもの視点で見てみよう。
まずは転倒などのため救急車で病院に運ばれたという場合。このときに運ばれる病院は「急性期病院」と呼ばれ「早期治療の回復」を目的とした病院である。骨折をしていた場合、治療、リハビリをしている期間は入院できるがその期間が終われば退院しなければならない。自宅に戻って生活できる環境があるかどうかを退院前に「家屋調査」が行われる。家族はその調査に協力する。たとえば玄関に段差はないか、家の動線に障害物はないか、手すりはあるか、風呂やトイレは利用できるかなど。その調査に基づいて自宅の環境整備を行う。この期間、患者は一般病棟を退院して地域包括ケア病棟に転院することができる。その入院期間中に退院後の生活ができるように本人にも家族にも準備をしてもらうのだ。
もし一人暮らしを続けるならこのときに本人のその意思確認をし、医療スタッフにその旨を伝える。そうすれば看護師は入院中に一人で服薬できるように、などトレーニングを行う。退院後の食事や入浴はどうするのか、リハビリはどうするのかは、訪問介護や訪問看護サービスの利用法を検討する。
ちなみに介護と看護は違いを理解しておくことは重要である。介護とは「日常生活の支援」が主であり、介護保険によってまかなわれる。利用者の生活の維持や向上が目的である。いっぽう看護とは「療養上の世話と診察の補助」が主であり健康保険によってまかなわれる。食事の介助や入浴のような身の回りの世話も療養上の補助であり医療行為である。したがって一見似たように見える業務でも介護と看護ではその意味はまったく別のものである。保険から支払われる介護職、看護職への報酬は業務ごとにその点数が定められている。なので「保険に定められている業務」以外は原則として受けることができない。たとえばヘルパー(介護職)に買い物に行ってもらうついでに生活必需品以外のもの(お酒やタバコなどの嗜好品など)を買ってきてもらうことはできない(原則としてと書いたのは「保険外サービス」として別途料金を支払うのであれば可能であるからである)。
つぎに入院をせずに自宅で治療を受けたり、終末期に退院をして自宅で最期を迎えることを希望する場合。今後「家で死ぬという選択」をするのはこのケースになる。在宅医療(「在宅ケア」とも呼ばれる)を行う場合、大切なのは医療側としっかり連携をとる体制をつくることである。病院にある「地域連携室」や「地域包括ケア病棟」に相談して訪問介護、訪問看護、訪問診療のサポートを受けられるようにする。医療界には今「多職種協働」というキーワードがある。地域包括ケアシステムのもと、これまで病院の中だけにいた医師、看護師、薬剤師、理学療法士、介護士、栄養士、メディカルソーシャルワーカー(MSW)といった職種がチームとなって地域と連携しようという動きである。患者家族はこういったチームと打ち合わせを行い、患者がこれから人生の最後をどのように迎えてほしいと思っているのか、家族としてはどうしていきたいのかのコンセンサスをとることが非常に重要になる。これは遠く離れた親がいる場合などにもぜひ足を運んで行ってほしい。
このような打ち合わせを厚生労働省では「人生会議」と名付けている。以前はアドバンスケアプラン(ACP)と呼ばれていたものを、より家族にも馴染むようにと2018年に制定したものだ。これまで日本の医療は「お医者さん任せ」のところがあった。それは医療が病院内で行われていたからだ。しかし今後、医療の現場は病院だけでなく、地域≒家にも広がっていくにつれて、患者やその家族がどのような最期を迎えたいか、「もしものとき」を突然迎えたときにどうするかを、事前に考えておくことが必要な時代になっていくのだ。
―自宅で死ぬということ― 著:小阿羅 虎坊(こあら・こぼ)
※「自宅で死ぬということ」は第2・4金曜日に更新します。
次回は7月12日にお届けしますのでお楽しみに。